二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問52 (学科3(建築構造) 問2)
問題文
図のような等分布荷重を受ける幅300mmの矩形断面の単純梁において、A点の最大曲げ応力度が10N/mm2となるときの梁のせいの値として、最も近いものは、次のうちどれか。ただし、部材の断面は一様とし、自重は無視するものとする。 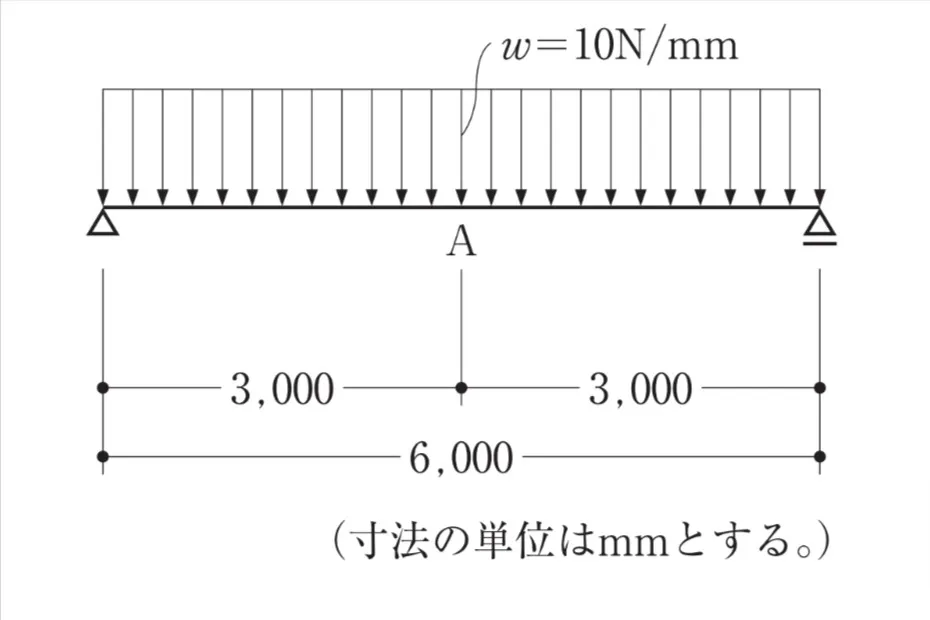
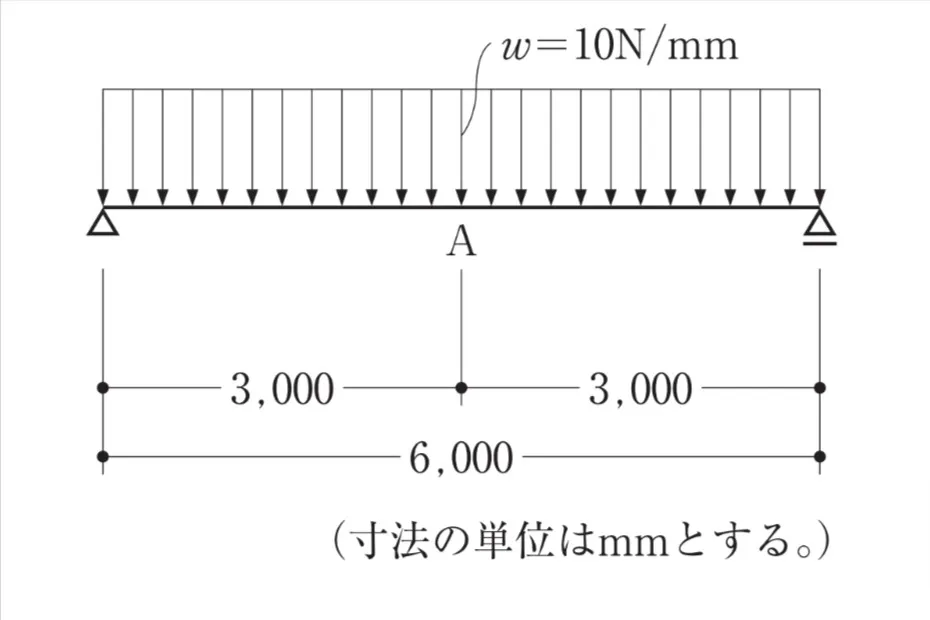
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問52(学科3(建築構造) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
図のような等分布荷重を受ける幅300mmの矩形断面の単純梁において、A点の最大曲げ応力度が10N/mm2となるときの梁のせいの値として、最も近いものは、次のうちどれか。ただし、部材の断面は一様とし、自重は無視するものとする。
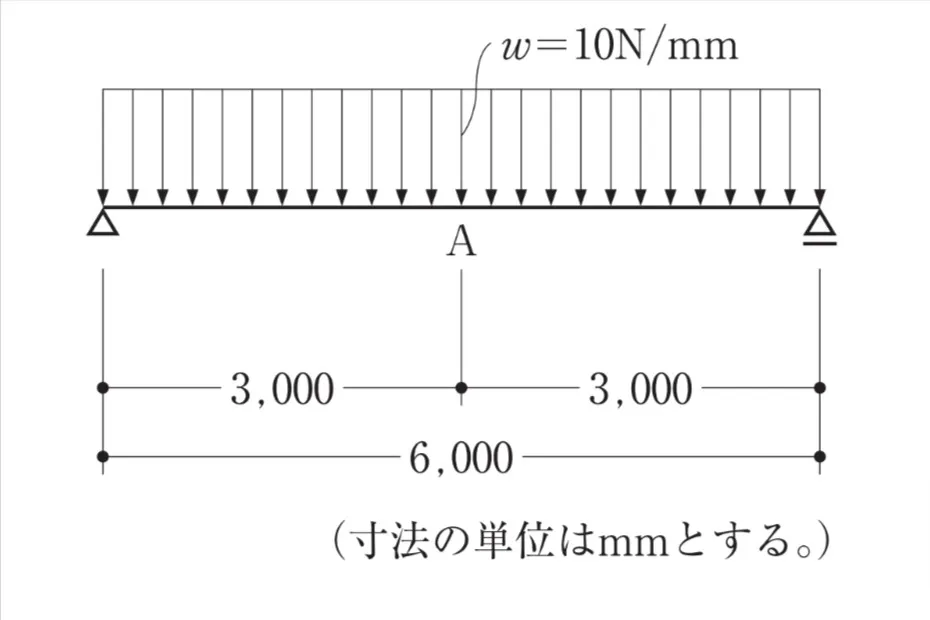
- 210mm
- 300mm
- 420mm
- 600mm
- 840mm
正解!素晴らしいです
残念...

この過去問の解説 (2件)
01
300 mmが最も近い値になります。
等分布荷重が掛かった幅300 mmの矩形断面において、最大曲げモーメントは
M=wL²/8=10 N/mm×6000²mm²/8=45000000N·mm です。
矩形断面の曲げ応力度は
σ=6M/(b h²) で表せます。
σ=10N/mm²、b=300mm を代入して h を解くと
h=√{6M/(b σ)}=√90000=300mm となります。
曲げ応力度は約20N/mm²となり、許容値10N/mm²を大きく上回ります。
断面が小さ過ぎます。
計算値と一致し、曲げ応力度がちょうど10N/mm²になります。
適切な断面寸法です。
曲げ応力度は約5N/mm²まで下がります。
強度上は安全ですが、材料を余分に使う大きさです。
曲げ応力度は約2.5N/mm²となり、必要以上に小さくなります。
過大な断面です。
曲げ応力度は約1.3N/mm²まで下がります。
著しく大きく、無駄が多い寸法です。
矩形断面の梁では、曲げ応力度 σ=6M/(b h²) を利用して必要な h を手早く求められます。
今回の条件では300mmが荷重に見合う最小限の大きさで、これより小さいと強度不足、大きいと材料の無駄が生じます。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
等分布荷重は、集中荷重W =10N/㎜×6,000㎜=60,000(N)=60(kN)におきかえて、中心に
作用すると考えます。
荷重が部材の中心に作用しているので、両支点が荷重を等分に負担します。
∴Vb=V c=30(kN)(上向き)
A点の曲げモーメントM AをA点の左側から求めます。
ΣMa=0より、(30kN×3,000㎜)-(30kN×1,500㎜)-Ma=0
Ma=45,000(kN・㎜)
=45,000,000(N・㎜)
=45×10⁶N・㎜ (下凸)
Z= bh²/6 = 300㎜ ×h²/6 =50h²㎜ ³
σb=Ma/Z = 45×10⁶/50×h²N/㎟
設問より、最大曲げ応力度が10N/㎟のときの梁せいを求める。
σb= 45×10⁶/50×h² =10N/㎟
h²= 45×10⁶/50×10 = 45×10⁶/5×10² =9×10⁴=90,000=300×300
∴h=300㎜
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問51)へ
令和6年(2024年) 問題一覧
次の問題(問53)へ